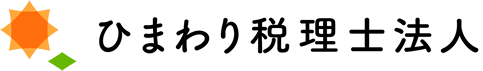相続 不動産 売却 税金
- 換価分割とは?譲渡所得の計算方法やメリット・デメリットなど
換価分割は、遺産を分ける方法のひとつで、財産を売却して現金化した後、現金を相続人で分ける手法です。譲渡所得の計算方法土地や建物を売却した際には、譲渡所得という税金がかかります。譲渡所得は、事業所得や給与所得とは異なる方法で計算します。 具体的には、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。取得費は、売却...
- 相続した不動産を売却する際にかかる税金について解説
相続により取得した不動産を売却する際には、さまざまな税金が関係してきます。特に気をつけたいのが「譲渡所得税」と呼ばれる税金です。本記事では、相続不動産を売却した際に発生する税金の種類や計算方法、節税のポイントについて解説します。譲渡所得税とは不動産などの資産を売却した際、購入時よりも高く売れた場合に発生する利益を...
- 医療法人の相続・事業承継について
一般的な株式会社で事業承継を行う場合、保有する株式が議決権となりますから、子どもへ事業承継する場合は自分の持っている株式をそのまま相続すれば事業承継が完了します。ところが、医療法人の社員総会では1社員が1議決権を有しています。そのため、医療法人を設立するときに出資した「出資持分」を相続するだけでは医療法人の事業承...
- 相続税対策のための生前贈与と贈与税について
生前贈与を行うことで、本人が亡くなった後に課税される相続税の課税対象の財産を減らせることから節税対策になります。もっとも、生前贈与には贈与税が課せられることから、生前贈与をしたほうが、かえって損をするおそれもあるので注意しましょう。 ・贈与税の基礎控除贈与税の課税方法の一つに暦年課税があります。これは、一年間に受...
- 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用及び収益を無償で認める法的権利をいいます。こうした権利が創出されたことにより、遺産の分割における選択肢の一つとしてや、被相続人の遺贈の選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させる...
- 相続税が払えない時の対処法
相続税が払えない場合に多いのは次の2パターンです。1つは「相続財産が不動産などの土地のみで現預金がない場合」、もう1つは「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままの状態である場合」です。 前者の場合「相続財産が不動産などの土地のみで現預金がない場合」とは、土地や建物のような評価額の高い不動産を保有しているものの、...
- 【1.6億円まで非課税】相続税の配偶者控除|ポイントや注意点は?
相続の際には相続税が課税されますが、すべての相続財産に対して課税されるわけではありません。相続税の課税金額は実際に手元にある相続財産から「控除」を差し引いた金額が相続税の課税対象額になりますが、その中でも「配偶者控除」は非常に大きな相続税の控除になります。配偶者控除のポイントや注意点について解説していきます。
- アパート経営は相続税対策になる?節税効果やポイントなど
相続税は累進課税制が採用されており、相続した遺産の額に応じて税率が高くなります。そのため、高額な資産を現金で残した場合、資産を承継する相続人が高額な相続税を納めなければならなくなります。相続税対策として現金で資産を残すのではなく、不動産を購入してアパート経営をすることが節税になると聞くことがあると思います。この記...
- 相続税の取得費加算の特例とは?適用要件、注意点など
不動産相続の際には、不動産を売却して現金化するということも一つの選択肢として挙がってきます。その際に、条件を満たすことによって相続した不動産の取得費に加え、それにかかる相続税を譲渡益から控除することができ、その分節税を行うことができます。本稿では、不動産における相続税の取得費加算の特例の適用要件や注意点について解...
- 遺贈でかかる相続税の計算方法や注意点について解説
遺贈を受け取った際の税金を計算するのは複雑でわかりにくいという方もいます。本記事では遺贈について、計算方法や注意点と併せて解説します。遺贈とは遺贈とは、亡くなった方(被相続人)が遺言によって、自分の財産を他の人に引き継ぐことを指します。被相続人が遺言を残している内容に従って、土地やお金などの財産を指定された人に渡...
- 相続税の課税対象となる財産とは
相続税の課税対象となる財産には、本来の相続財産、みなし相続財産、相続開始時よりも前の3年以内になされた生前贈与や相続時精算課税の特例を適用し生前贈与された財産があります。これら以外の財産は、非課税財産として相続税の課税対象外となります。 ・本来の相続財産本来の相続財産とは、被相続人の遺産のうち換金性のある財産のこ...
- 不動産を相続したときの手続きとかかる税金
親族が亡くなったとき(民法882条)、亡くなった方(被相続人)の財産や借金は親族である相続人に承継されることとなります(同法896条)。では、不動産を相続したときにはどのような処理がなされるのでしょうか。 まず、不動産を相続するためには、不動産がどれぐらいの金銭的価値を持っているのか把握しなければなりません。現在...
- 事業承継の3つの方法とは
親族間で事業承継を行うことによって、相続による事業承継を行うことができる、従業員や取引先にも「親族」という理由で信頼を得やすいというところが大きなメリットとして挙げられます。一方親族だからといって経営の手腕がいいというわけではないため、事業承継をした後の経営状況には不安が残りやすい事業承継になります。 ②親族以外...
- 生前贈与で活用できる贈与税の非課税枠について
しかしながら、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子ども、孫に対する生前贈与の場合には相続時精算課税制度が適用されることで、2500万円の財産を限度として、一旦贈与税を納める必要はなく、相続が生じる時まで納税を猶予されます。これを非課税枠といいます。そして2500万円の限度を超えてしまった場合には、その超過部...
- 不動産は相続税対策に有効?具体的な方法について解説
相続税対策として不動産を所有することは節税効果につながる、ということはよく出てくる代表的な手法です。なぜ不動産を所有していることが相続税対策として有効なのでしょうか。解説していきます。 ■不動産の評価額にポイントがある相続税の評価額は不動産においては固定資産税評価額や路線価によって定められます。もし1億円の現金を...
- 相続税の更正の請求が発生するケース|手続き方法も併せて解説
相続税を申告した後、払いすぎや申告内容に間違いがないか不安に思う方もいます。本記事では、相続税の更正の請求が必要になるケースと、手続き方法について解説します。相続税の更正の請求が発生するケース相続税の更正請求とは相続税を納めた後に、実際の税額がもっと少ないと判明した場合に行う申請手続きです。反対に、相続税を少なく...
- 「相続税についてのお尋ね」が届くのはなぜ?無視するとどうなる?
相続が発生した後、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。これは相続税の申告漏れを防ぐために送られてくる確認書類です。本記事では、「お尋ね」が届く理由や対応方法、無視した場合のリスクについて解説します。「相続税についてのお尋ね」とは?「相続税についてのお尋ね」とは、相続が発生した際に、...
- 法人税の種類
税務申告で申告を行うものとして、法人税がありますが、法人税の中でも多くの種類の税金があります。 ・法人税ここでの法人税は「国税」としての法人税です。前述した広義での「法人税」は法人が支払うべきすべての税金をまとめて「法人税」といいます。狭義での「法人税」は法人の利益に対して納めるべき国税です。・消費税消費税は、サ...
- 相続税申告を税理士に依頼するメリット
相続税の節税対策には、生前贈与による贈与税の基礎控除や非課税の特例を利用することや、土地や建物の評価額の減額措置を利用するなど様々な方法があります。また、両親のうち一方の親が亡くなった場合の一次相続と、その後もう片方の親が亡くなった場合の二次相続があります。一次相続の際に、二次相続にかかる相続税の課税を念頭にいれ...
- 相続税申告の流れ
・被相続人の亡くなった直後相続が開始されると、まずは、被相続人の死亡届、保険証の返却、世帯主の変更届を行います。また、被相続人に所得税の納税義務がある場合は、被相続人が亡くなった日の翌日から4カ月以内に相続人が代わりに準確定申告・納税を済ませます。次に、相続税申告は、相続人が誰であるか、相続財産は何かを特定する必...
- 相続税の基礎控除について
相続税は、被相続人の遺産総額のうち、法定相続人の人数に応じて算出された基礎控除額の分までは非課税となります。したがって、基礎控除の仕組みを知ることで、相続税の納税義務があるのかどうかを知ることができます。 ・相続税の発生相続税は、被相続人の遺産総額が基礎控除額を超えた部分の金額(課税対象額)に発生します。そして、...
- 大阪市の記帳代行はひまわり税理士法人へ
適切な税金額を納めるためにも、記帳はしっかりと行う必要があります。 もっとも、記帳は全ての取引を計上しなければならず、時間と体力がかかり、骨の折れる作業と思う方が多いかと思います。そのような方は、税理士による記帳作成の代行サービスを依頼することをお勧めします。記帳代行のメリットは、何と言っても煩雑な手続きを全て代...
- 相続税が軽減される配偶者控除はどんな制度?
■相続税における配偶者控除とは相続税における配偶者控除制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が一定金額を超過するまでは配偶者の相続税は非課税となる制度をいいます。では、実際にいくらから配偶者に相続税が発生するのでしょうか。 〇1億6千万円〇配偶者の法定相続分相当額 以上の金額を超過し...
- 相続税はいくらからかかる?
相続が発生した際には相続税がかかりますが、すべての相続財産に対して課税されるわけではなくある一定の相続財産までは相続税がかかりません。相続税は基礎控除と呼ばれるすべての相続において適用される控除や生命保険金の非課税枠などといった相続財産から相続税の計算として除外することの出来る金額があります。これらの控除枠を適用...
- 銀行融資の審査を通すコツ
仮に返済ができなくなった場合には、現金ではなく不動産を銀行へ差し出すことによって銀行側は融資金額が回収できる可能性があります。そのため、銀行は担保などの保証能力が十分かということも見ます。十分に資産があることをアピールしましょう。 このいずれかにも自信がない場合には、事業計画書を念入りに作成して今後の事業が成功す...
- 起業をお考えの方へ~知っておくべき資金繰りの基礎知識~
ひまわり税理士法人は、大阪市・堺市・箕面市・枚方市をはじめとする、関西圏を中心に西日本全域で皆さまからのご相談を承っております。 相続でお悩みの際は、弊社までご相談ください。ご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
- 相続税の申告期限|過ぎた場合どんなペナルティがある?
相続の際には相続税がかかります。しかし、相続税を期限内に支払えなかった場合どのようになるのでしょうか。 ■相続税の期限相続税の申告と納税は相続が発生してから10か月以内に行う必要があります。しかし、相続税の申告においては遺産分割協議や準確定申告などであまり時間が取れないことが多く、期限内に申告納税できるか不安なこ...
- 相続時精算課税制度とは?今後の改正内容も併せてわかりやすく解説
相続時精算課税制度とは、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付することで累計2,500万円までの贈与について、非課税になる制度です。制度の利用においては、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告する必要があります。また、同じ父母や祖父母からの贈与は、累計が2,500万円に達するまで何度...
- マンションの相続税評価額とは?計算方法や相続で使える特例など
相続手続きで被相続人(亡くなった人)の財産にマンションが含まれている場合、「マンションの相続税評価額」を計算する必要があります。マンションの相続税評価額は、戸建てとは計算方法が少し違います。建物と土地を別々に計算しなければなりません。 本稿では、マンションの相続税評価額の仕組みと計算方法、また相続税を節税するため...
- 相続税の障害者控除|適用要件や注意点など分かりやすく解説
相続税を減税できる税額控除の一つに「障害者控除」があります。相続税の障害者控除は、相続人の中に障害者がいる場合に適用可能です。本稿では、相続税の障害者控除の適用要件や注意点を解説します。相続税の障害者控除の適用要件相続税の障害者控除は、被相続人が亡くなった時点で、相続人が障害者であり85歳未満の場合に適用される特...
- 【種類別に解説】未支給年金にも相続税はかかる?
未支給年金を遺族が受け取る場合、年金の種類によって相続税がかかる可能性があります。この記事では、未支給のどの年金に相続税がかかるのか紹介します。年金の種類年金は、公的年金、企業年金、個人年金保険という3つの種類に分けられます。それぞれの年金の特徴と未支給年金について解説します。公的年金公的年金とは、国民年金や厚生...
- 住宅取得等資金贈与の非課税とは?制度の概要や手続きなど
万円)が、相続時精算課税では基礎控除(110万円)および特別控除(2,500万円)が適用されます。まとめ住宅取得等資金贈与の非課税制度は、親や祖父母から住宅購入資金の援助を受ける際に、贈与税の負担を軽減できる制度です。ただし、適用には多くの要件や提出書類があるため、事前の確認と準備が重要になります。制度の詳細や適...
- 決算が赤字の場合の法人税の取り扱い|無申告でもいいの?
億円を超える法人や、電力・ガスといった特定の業種に該当する場合には、たとえ赤字であっても、資本金などを基準に税金が発生するケースがありますので注意が必要です。税務調整による課税所得の発生会計上の赤字であっても、法人税の税務調整により課税所得が発生するケースもあります。たとえば、交際費や寄附金、役員賞与などは一部損...
当事務所が提供する基礎知識
-
住宅取得等資金贈与の...
住宅の購入や新築、増改築などを行う際に、親や祖父母から資金援助を受けるケースは少なくありません。その際、通常であれば贈与税の対象となりますが、一定の条件を満たすと「住宅取得等資金贈与の非課税制度」を活用して、一定額まで贈 […]

-
医療法人の相続・事業...
日本は現在少子高齢化社会と言われていますが、医療業界も高齢化が進んでいます。診療所の医師は平均年齢が60歳近く、2割が70歳を超えていると言われています。しかし、医療法人の事業承継は難点もあり、なかなか事業承継が進んでい […]

-
創業融資のメリット・...
創業融資とは、会社を設立する際に自分だけで必要資金を賄うことができない場合に、他者からお金を借りることを指します。その主な手段として、日本政策金融公庫からの創業融資が考えられます。しかし、創業融資にはメリットとデメリット […]

-
顧問税理士とは
顧問税理士とは、法人と弊社の税理士とで顧問契約を結ばせていただいて、決算などのみではなく、すべての税務に関することを弊社の税理士がお手伝いをさせていただくことが出来る仕組みです。税務顧問が出来ることは、記帳代行や決算書類 […]

-
「相続税についてのお...
相続が発生した後、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。これは相続税の申告漏れを防ぐために送られてくる確認書類です。本記事では、「お尋ね」が届く理由や対応方法、無視した場合のリスクについて解 […]

-
起業をお考えの方へ~...
起業をする際には資金が必要になりますが、起業をした後にも「資金繰り」が非常に重要になってきます。資金繰りとは一体どのようなものなのか、悪化させないためには何が必要なのかということについて解説していきます。 ■資 […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 相続 相談 税理士 堺市
- 税務 相談 税理士 大阪 西区
- 税務 相談 税理士 箕面市
- 起業支援 相談 税理士 枚方市
- 独立支援 相談 税理士 箕面市
- 独立支援 相談 税理士 堺市
- 相続 相談 税理士 枚方市
- 独立支援 相談 税理士 枚方市
- 相続 相談 税理士 大阪市
- 創業支援 相談 税理士 箕面市
- 記帳代行 税理士 堺市
- 税務 相談 税理士 枚方市
- 起業支援 相談 税理士 堺市
- 記帳代行 税理士 枚方市
- 相続税申告 相談 税理士 大阪市
- 相続税申告 相談 税理士 枚方市
- 創業支援 相談 税理士 枚方市
- 事業承継 相談 税理士 堺市
- 起業支援 相談 税理士 大阪 西区
- 独立支援 相談 税理士 大阪 西区
税理士紹介
事務所概要
| 名称 | ひまわり税理士法人 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D |
| 連絡先 | TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| 初回相談 | 無料 |