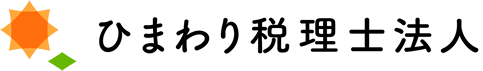相続税の連帯納付義務とは?負担割合やペナルティなど
相続税にはさまざまなルールがありますが、その中でも注意したいのが「連帯納付義務」です。
相続税は自分の分だけ納税すればよいと思われがちですが、実際にはそうではありません。
本記事では、相続税の連帯納付義務の概要や負担割合、ペナルティなどについて紹介します。
相続税の連帯納付義務とは
相続税では、各相続人がそれぞれの相続分に応じて税額を負担します。
しかし、国にとっては全額が納められるかが重要です。
そのため、法律上はすべての相続人が相続税の納税について連帯責任を負う仕組みになっています。
これを「連帯納付義務」と呼び、自分の税額をきちんと納めても、他の相続人が滞納すれば、その分についても請求される場合があります。
なお、通常は相続税の納付期限後、本人が滞納すればまず本人へ通知が届き、未納が続けば連帯納付義務者に通知され、それでも払わなければ請求される流れとなります。
負担金額の上限
連帯納付義務者が負担するのは自ら相続した財産の価額までと定められています。
したがって、無制限に他人の分まで背負うわけではありません。
連帯納付義務の存続期間
相続税の連帯納付義務は、無期限に続くわけではありません。
国税の納税義務については一定の時効が設けられており、相続税の連帯納付義務も原則として納期限から5年間で消滅します。
延滞税と利子税
相続税を納付期限までに納めないと延滞税が発生します。
延滞税は本来の納税義務者が支払うべきものですが、未納があれば連帯納付義務者にも支払い義務が及びます。
ただし、肩代わりする場合に一定の要件を満たせば、延滞税の代わりに利率の低い利子税が課される制度があります。
この軽減措置はあくまで代わりに支払う側に適用され、滞納者本人の延滞税が減るわけではありません。
求償権の仕組み
連帯納付義務者が他の相続人の税金を立て替えて支払ったときには、求償権が認められています。
これは、負担の公平性を保つために、本来の納税義務者に対して肩代わりした金額を請求できる権利となります。
まとめ
相続税の連帯納付義務は、すべての相続人にとって無視できない重要な仕組みです。
自分の負担分だけ納めれば安心というわけではなく、他の相続人の未納分まで背負う可能性があるため、家族全体で協力することが重要です。
相続税の納税に関してお悩みの場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
マンションの相続税評...
相続手続きで被相続人(亡くなった人)の財産にマンションが含まれている場合、「マンションの相続税評価額」を計算する必要があります。マンションの相続税評価額は、戸建てとは計算方法が少し違います。建物と土地を別々に計算しなけれ […]

-
相続税の連帯納付義務...
相続税にはさまざまなルールがありますが、その中でも注意したいのが「連帯納付義務」です。相続税は自分の分だけ納税すればよいと思われがちですが、実際にはそうではありません。本記事では、相続税の連帯納付義務の概要や負担割合、ペ […]

-
相続税対策のための生...
生前贈与とは、第三者に対して存命中に財産を無償で譲渡することです。生前贈与を行うことで、本人が亡くなった後に課税される相続税の課税対象の財産を減らせることから節税対策になります。もっとも、生前贈与には贈与税が課せられるこ […]

-
飲食店の事業計画書の...
事業を行っていくにあたって事業計画書は事業の今後の流れを客観的にアピールできる資料として大切なものです。特に飲食店の場合には開業資金や内装の改装資金などで金融機関から資金調達をすることも多いかと思いますので特に重要な資料 […]

-
起業をお考えの方へ~...
起業をする際には資金が必要になりますが、起業をした後にも「資金繰り」が非常に重要になってきます。資金繰りとは一体どのようなものなのか、悪化させないためには何が必要なのかということについて解説していきます。 ■資 […]

-
相続税申告の流れ
・被相続人の亡くなった直後相続が開始されると、まずは、被相続人の死亡届、保険証の返却、世帯主の変更届を行います。また、被相続人に所得税の納税義務がある場合は、被相続人が亡くなった日の翌日から4カ月以内に相続人が代わりに準 […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 記帳代行 税理士 枚方市
- 相続 相談 税理士 大阪市
- 医業承継 相談 税理士 堺市
- 税務 相談 税理士 箕面市
- 相続税申告 相談 税理士 箕面市
- 税務 相談 税理士 大阪 西区
- 独立支援 相談 税理士 枚方市
- 医業承継 相談 税理士 枚方市
- 事業承継 相談 税理士 堺市
- 起業支援 相談 税理士 大阪 西区
- 税務 相談 税理士 大阪市
- 事業承継 相談 税理士 大阪市
- 医業承継 相談 税理士 大阪市
- 独立支援 相談 税理士 箕面市
- 税務 相談 税理士 枚方市
- 記帳代行 税理士 大阪市
- 創業支援 相談 税理士 堺市
- 事業承継 相談 税理士 箕面市
- 相続税申告 相談 税理士 枚方市
- 記帳代行 税理士 箕面市
税理士紹介
事務所概要
| 名称 | ひまわり税理士法人 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D |
| 連絡先 | TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| 初回相談 | 無料 |